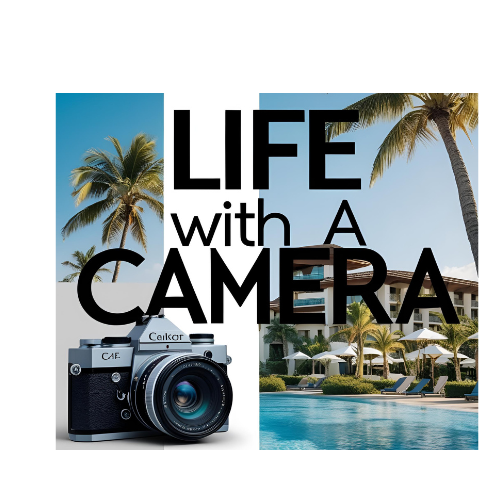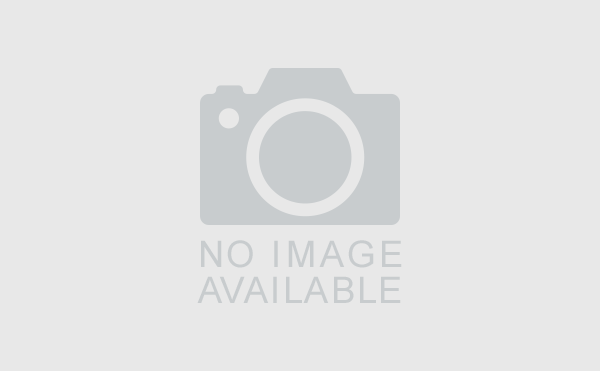音が呼吸する庭──常栄寺・雪舟庭で体験した《Forest Symphony》
今回、私は山口県山口市宮野に位置する常栄寺・雪舟庭に行ってきました。
そしてそれと同時に坂本龍一さんとYCAMの下で監修された、Forest Symphonyの体験もしてきましたので、それに関してもお伝えしようと思います。

↑↑↑↑↑↑
山口情報芸術センター(YCAM)
山口情報芸術センター
山口情報芸術センター(YCAM)は、現代アートやメディアアートを中心に展示・公演を行う文化施設です。アーティストと研究者が協働し、新しい表現や技術を開発する研究拠点としての役割を持ち、教育ワークショップや地域交流活動も積極的に展開しています。図書館や映画館も併設され、芸術とテクノロジーを融合させながら市民に開かれた文化発信の場となっています。
①坂本龍一監修のForest Symphonyとは

「Forest Symphony」は、坂本龍一さんが監修したアートプロジェクトです。
森に設置されたセンサーが風や雨、木々の揺れなど自然環境のデータを収集し、それをリアルタイムに音へと変換する試みです。
まるで森そのものが楽器となり演奏しているような体験ができ、自然と人間の関わりについて改めて考えさせてくれる作品です。
坂本さんが大切にしてきた「環境と音楽の融合」を感じられる、非常にユニークな芸術表現となっています。
場内には12面体のスピーカーが8つあり、そのスピーカーたちが自然環境をもとに生成したデータをから電子音が響く設計になっており
その音たちは常栄寺の川のせせらぎの音や樹木の音であったり
山口周辺のお寺、清水寺などから録音した音声を100倍速で再生したり、オーストラリアの寺院での音なども再生していたりと、様々な音を立体的にかんじることができ、なんともいえない神秘的な雰囲気を感じられることができます。
常栄寺に入ると各スピーカーから流れている音の説明がボードに記載されており、その音たちについて簡単に知ることができます。
またわからないときにはすぐそばに、山口情報芸術センターのスタッフの方が優しく教えてくださるので、聞いてみるといいですよ!
②常栄寺・雪舟庭の特徴
山口市にある常栄寺雪舟庭(じょうえいじ・せっしゅうてい)は、室町時代の画僧・雪舟等楊が築いたと伝えられる名園で、国の史跡・名勝にも指定されています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E8%88%9F ←雪舟についてのウィキペディア
約900坪に広がる庭は、まるで一幅の水墨画をそのまま立体化したかのような静謐な空間です。
この庭の特徴は、まず池泉回遊式庭園であること。中央の心字池を巡りながら歩くことで、見る位置によってまったく異なる表情が現れます。
北側にはかつて水が流れていた滝石組があり、園全体にリズムと動きを与えています。
さらに、池畔や芝地には力強い立石が随所に置かれており、使われているのは近隣で産出される硬質な輝岩。
自然の岩肌をそのまま生かした配置は、室町庭園らしい骨太さを感じさせます。
鑑賞の仕方にも工夫があり、本堂正面からの遠近法的な眺め、西側からの雄大な眺め、そして書院跡からの側景――
三つの視点が用意され、歩くごとにまったく異なる庭の顔と出会えます。
また、この庭は四季折々の変化も大きな魅力です。春は桜が華やぎ、夏は深い緑に包まれ、秋は紅葉が池を彩り、冬は雪景色が水墨画のような趣を生み出します。
借景となる周囲の山々と調和し、訪れるたびに違った景色を楽しむことができるのです。



常栄寺・雪舟庭の歴史
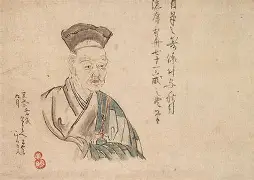
常栄寺雪舟庭は、室町時代に活躍した画僧・**雪舟等楊(せっしゅう とうよう)**が作庭したと伝えられています。
雪舟は水墨画の巨匠として知られる一方で、中国・明に渡って本格的な水墨画を学び、その構図や感性を庭園にも応用しました。
この庭が築かれたのは、山口が大内氏の治世によって「西の京」と呼ばれるほど文化が栄えた時代。
京都の戦乱を逃れた多くの文化人が山口に集い、茶の湯や連歌、絵画や建築などが大いに発展しました。
その中心的存在の一人が雪舟であり、この常栄寺の庭は、まさに大内文化と雪舟の芸術が融合した貴重な遺産です。
特徴的なのは、庭そのものが水墨画の世界を立体的に表現している点です。
心字池や立石の配置は遠近感を強調し、借景の山々を取り込むことで一枚の絵画のような奥行きを生み出しています。これは絵師・雪舟ならではの独自の発想であり、日本庭園史においても重要な意味を持つ存在といえます。
今日では、常栄寺雪舟庭は国の史跡・名勝として保護され、四季を通じてその美しさを鑑賞できる場となっています。静かに佇む庭に身を置くと、室町の人々が育んだ美意識と雪舟の芸術観が、時を越えて響いてくるようです。
常栄寺×坂本龍一監修「Forest Symphony」の鑑賞ポイント
常栄寺×坂本龍一監修Forest Symphonyの鑑賞ポイントについてです。
今回は常栄寺を単体としてみた時の鑑賞の仕方と、Forest Symphonyがコラボしているからこそ味わえるような
鑑賞ポイントについてお伝えしていきます。
そしていい写真を撮りたい、いい動画を作成したいという方向けに僕が実際に撮影した時に気を付けていたポイントやいいように映るポイントについて解説している記事もありますのでよかったらそちらも見てください!
※リンク掲載までしばらくお待ちください
①常栄寺内の畳の上で
常栄寺には、畳の上で安らぐことができるスペースがあるのですが、そこに坂本龍一さんが監修した「Forest Symphony」のスピーカーが設置されています。
そこには座布団のような黒いクッションがあり、非常に安らぐことができます。
そしてそこで安らぎながら、音を楽しむことができます。
さらにそこから常栄寺の庭を鑑賞することもできます。
音を聞き、安らぎながら、庭園を見る。
間違いなく全員が気に入ってくれるでしょう!
②庭園をゆっくり
常栄寺の庭園は自由にその周りをまわることができます。
庭園の中に入ることは許されておりませんが、その周りには緑豊かに広がる景色に囲まれ、
川の流れの音を聞きながら、回ることができます。
見る視点、角度を変えることによって見えてくる景色が異なり、飽きを感じさせません。
最後に
今回、常栄寺に行ってみて感じたのはこの場所が感じさせる落ち着きと何とも言えない落ち着きは特別なものだと感じました。
そして、夏真っただ中な期間に行ったのにもかかわらず、エアコンを使わずとも涼しいことになぜそうなっているのかが気になりました
今回の取り組み「Forest Symphony」には坂本龍一さんに興味がなくても、常栄寺の歴史について知らなくても、十分に体験することが可能です。
ぜひ、少しでも気になっていただいたら、足を運んでみてはいかがでしょうか